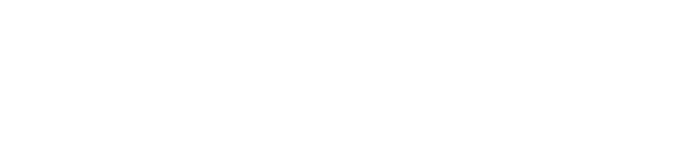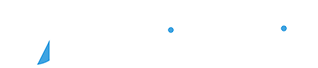ダイエットをしているわけでもなく、いつも通りの食事をしているのに体重が減少している場合、何らかの疾患が隠れている可能性があります。
体重減少を起こす疾患はさまざまですが、ほかの自覚症状がほとんどない場合は慢性肝炎・肝硬変・がんなどのおそれがあります。
体重が減少する主な理由は、エネルギー不足、エネルギー消費の増加、エネルギー漏れの3つです。それぞれのケースについて具体的に見てみましょう。
体重が減少してしまう原因
エネルギー不足
胃がんや大腸がんをはじめ、がんが進行すると、がんが消化管を圧迫して食事ができなくなってしまいます。
また、がん細胞からつくり出される物質が代謝異常を起こして、食べられなくなることもあります。抗がん剤治療の副作用やストレスも、食欲不振でエネルギー不足を招く原因です。
がんのほかに食事がとれずにエネルギー不足につながりやすい疾患としては、逆流性食道炎・胃潰瘍・潰瘍性大腸炎・クローン病・膵炎・胆石症などがあります。
エネルギー消費の増加
がんが増殖してエネルギー消費量が増えることで、痩せてしまうケースも少なくありません。がん細胞が生きるためには多くのエネルギーが必要です。そのため、栄養を奪い取ってしまいます。
なかでもブドウ糖は、がん細胞にとっても重要なエネルギー源です。白米・麺類・パンなどに豊富に含まれる炭水化物が消化・分解されてブドウ糖になり、がん細胞がそのエネルギーを消費してしまうのです。
エネルギー漏れ
エネルギーが漏れてしまう疾患もあります。たとえば、蛋白漏出胃腸症では腸管の表面からタンパク質が排出されてしまいます。また、寄生虫にエネルギーを奪われてしまうケースもあります。
受診・検査の目安
体重減少のほかにも症状がある場合はもちろん、ほかに自覚症状がなくても次のような場合には内科を受診してください。
・6か月で4〜5kg程度痩せてしまった
・6か月で体重が5%以上減少した
また、期間や体重に限らず、不安なときはいつでもご相談ください。
まとめ

明らかに食欲が落ちたときはもちろん、食欲があるのに体重が落ちている場合は、早めの検査が大切です。
当院では、丁寧な問診のうえ、必要な方には胃カメラ検査や大腸カメラ検査をおこないます。病原が見つかった場合、状態によってはすぐに切除可能です。
経験豊富な専門医が苦痛の少ない視鏡検査を提供いたしますので、胃カメラや大腸カメラが不安な方も安心していらしてください。